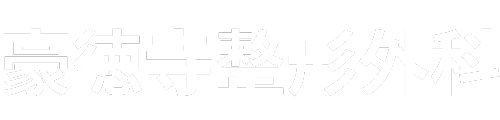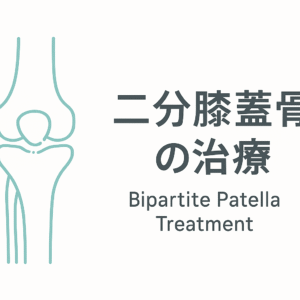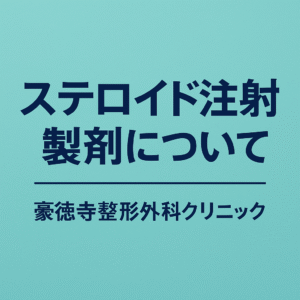扁平足(へんぺいそく)の原因・症状と治療法 ―世田谷区・豪徳寺整形外科クリニック 院長解説ブログ―
導入:土踏まずがなくて足が疲れやすい…それ、放っておいて本当に大丈夫?
「長時間歩くと土踏まずが痛む」「子どもの足裏がペタッと床についている」――こうしたお悩みは、扁平足が関係しているかもしれません。多くの場合は生活上の工夫で改善できますが、放置すると足だけでなく膝や腰にも負担が及ぶことがあります。当院では小児から成人まで幅広く診療しており、安心してご相談いただけます。
1. 扁平足とは?:土踏まず(内側縦アーチ)が低下した状態
足の骨が弓なりにつくるアーチ構造は、歩行時の衝撃を吸収するサスペンションの役割を担います。このアーチがつぶれて平らになった状態が扁平足です。小児期は成長につれて自然にアーチが形成されますが、成人後に痛みや機能障害が続く場合は治療が必要となることがあります。
1-1 背景・原因
- 先天的要因:生まれつきアーチ形成に必要な骨配列や靱帯のゆるみが見られるケースがあります。ゆったりめの靴で過ごす文化なども影響します。
- 後天的要因:加齢や体重増加、長時間の立ち仕事で足底筋や後脛骨筋が疲労・断裂し、アーチを支えきれなくなることがあります。
- スポーツ・靴の影響:クッション性に乏しい靴やサイズ不適合のシューズはアーチ部のストレスを増やします。
2. 考えられる関連疾患
アーチ低下が進むと扁平足以外にも複数の足部障害を招く可能性があります。
- 足底腱膜炎
アーチが低いと母趾球~踵を結ぶ足底筋膜が過緊張し、朝の一歩目に強い痛みを感じます。 - 後脛骨筋腱機能不全(PTTD)
アーチ支持の要である後脛骨筋腱が損傷し、成人期に痛みと急激な扁平化を来す疾患です。 - 外反母趾・シンスプリントなど
足のバランス変化が膝下のアライメントにも影響し、骨突出やすねの痛みを引き起こします。
3. 診断・検査
当院では以下の手順で総合的に評価します。
- 視診・触診・姿勢評価
立位で土踏まずの高さ、踵の傾き、歩行パターンを確認。 - X線撮影
立位側面像で距骨と舟状骨の角度(Meary 角)などを測定し、重症度を判定します。 - 超音波・MRI
痛みが強い場合は後脛骨筋腱や足底腱膜の状態を詳細に評価します。
4. 治療内容
4-1 保存的治療(まずはここから)
- インソール療法
オーダーメイドまたは既製品でアーチを適切に支え、痛みと疲労を軽減します。靴に合わせて調整可能です。 - 足底筋・後脛骨筋トレーニング
タオルギャザー(タオルを足指でたぐり寄せる運動)やカーフレイズでアーチを持ち上げる筋力を鍛えます。 - 体重管理・靴の見直し
体重過多はアーチの沈下を促進します。クッション性とフィット感に優れたシューズ選びも重要です。
4-2 外科的治療(保存治療で改善しない例)
重度変形や後脛骨筋腱が断裂している場合は、腱移行術や骨切り術でアライメントを矯正します。手術適応は慎重に検討し、術後は装具とリハビリが欠かせません。
5. 当院での対応
- 総合評価と段階的プラン
診察当日に症状とライフスタイルに合わせた治療プランを提案します。 - リハビリ専属スタッフ常駐
姿勢・歩行指導を実施し、トレーニング継続をサポートします。
まとめ・受診案内
扁平足は「よくある足の形」と軽視されがちですが、放置すると足・膝・腰へ連鎖的に負担が広がることがあります。痛みが続いたりスポーツパフォーマンスに影響したりする場合は、早めの診察が回復への近道です。お気軽にご相談ください。
要約(重要ポイント)
- 扁平足はアーチ低下により衝撃吸収能が落ちる状態で、疲れや痛みの原因となる。
- 原因は先天的要素と後天的要素が混在し、加齢・体重増加・靴選びも影響。
- 関連疾患として足底腱膜炎や後脛骨筋腱機能不全などが続発する可能性がある。
- 診断は視診・触診・X線で重症度を評価し、治療方針を決定。
- 保存療法ではインソールと筋トレが中心で、生活習慣の見直しが重要。
- 外科的手術は重度例に限り検討し、術後リハビリが必須。
- 豪徳寺整形外科クリニックでは多職種で連携し、子どもの足育から成人の外科治療まで幅広く対応。
- 早期受診が将来の関節障害を防ぐ鍵となるため、痛みが続く場合は専門医へ。
豪徳寺整形外科クリニックの受診をご希望の方へ
- 所在地:東京都世田谷区豪徳寺3-1-52
- アクセス:小田急線「豪徳寺駅」徒歩5分/東急世田谷線「山下駅」徒歩5分
- 診療時間:平日 9:00-12:00 / 14:30-18:00、土曜 午前のみ
- 電話:03-5451-7878
※当院の予約は時間帯予約制(30分幅)です。予約なしでも受診可能ですが、混雑状況によりお待ちいただく場合があります。