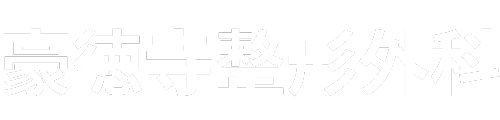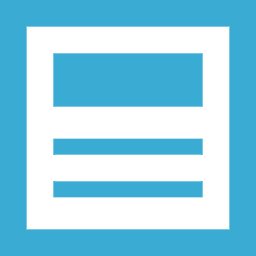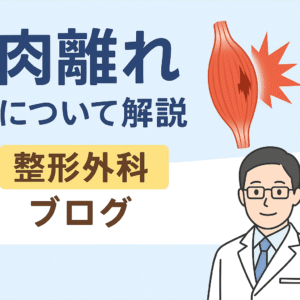カロナールは効かない?アセトアミノフェンの正しい効果と副作用、ロキソニンとの違いを医師が解説
導入:その痛み、“やさしい薬”で和らぐかもしれません
「飲むと胃がムカムカする」「年齢的に強い鎮痛薬は心配」――そんな声を外来でよく耳にします。整形外科医として私がまず検討するのがアセトアミノフェン製剤〈カロナール〉です。NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)より胃腸や腎臓への負担が小さく、高齢の方でも比較的安全に痛みを抑えられる一方、“たくさん飲んでも大丈夫”ではなく、肝機能チェックが不可欠です。本記事では、正しい用量設定から注意点までを総合的に解説します。
カロナールとは? ── 作用メカニズムと基本データ
カロナール(一般名:アセトアミノフェン)は、脳内の「痛みスイッチ」を穏やかに抑えることで鎮痛・解熱効果を発揮します。炎症そのものを強力に抑えるNSAIDsと異なり、胃粘膜や腎血流に深刻な影響を与えにくい点が最大の特長です。WHOの鎮痛薬ステップでも“第一選択”として推奨され、**日本での最大投与量は成人1日4,000 mg(体重60 kg未満では60 mg/kgまで)**と定められています。
痛みを抑えるポイント:量を適切に“増やす”ことがカギ
軽度〜中等度の痛み(変形性膝関節症、腰痛、骨折後の鈍痛など)では、単回300 mg程度から開始し、痛みが残る場合は単回500 mg〜1,000 mgまで段階的に増量することで効果が高まります。これは「血中濃度を一定レベルまで引き上げると鎮痛効果が頭打ちになる」という薬理データに基づく“容量依存的作用”です。一方、短時間での繰り返し服用・長期服用では肝障害リスクが高まるため、①1回用量1,000 mgを超えない ②4〜6時間あけて服用 ③1日4,000 mgを超えないという三つの基本ルールを必ず守りましょう。
高齢者にも安全と言われる理由
- 胃腸障害が少ない
NSAIDsで問題となる胃潰瘍・十二指腸潰瘍は、アセトアミノフェンでは極めてまれです。食欲が落ちやすい高齢者でも続けやすいメリットがあります。 - 腎機能への負担が小さい
NSAIDsは腎血流を下げるため、脱水や慢性腎臓病の方では注意が必要です。アセトアミノフェンはその影響が少なく、腎機能に悪い患者さんにもつかえます。 - 抗血小板作用をほぼ示さない
ワーファリンやDOACを服用中でも出血リスクが上がりにくく、整形外科手術の周術期にも使いやすい薬剤です。
ただし「肝機能チェック」が必要
アセトアミノフェンは肝臓で代謝される過程で、一部が**肝毒性を持つ代謝物(NAPQI)**に変換されます。通常はグルタチオンが速やかに無毒化しますが、
- アルコール多飲
- B型・C型肝炎など既存の肝疾患
- 低栄養や高齢によるグルタチオン低下
が重なると解毒が追いつかず、急性肝障害を起こすことがあります。当院ではスタート時と増量時にAST・ALTを採血し、安全域を確認してから処方量を決定しています。
当院での処方フロー
- 問診・診察:痛みの種類(炎症性/神経性など)と強さを評価
- 初期用量300 mg〜500 mgで2〜3日トライ
- 効果不十分なら1回500 mg〜1,000 mgへ増量し再評価
- **定期採血**で肝酵素・腎機能をチェック
- 他の鎮痛薬やリハビリ併用で“多角的疼痛マネジメント”を提案
もし冬場の膝などの関節痛で痛み止めを飲んでいるなら、こちらの対策もあわせてご覧ください 冬に膝が痛む本当の理由とは?冷えからくる痛みに効果的な対策と温め方を専門医が紹介
カロナール(アセトアミノフェン)とロキソニンの違い
患者さんから一番多い質問のひとつが「結局どっちがいいの?」です。
結論から言うと、**痛みのタイプ(炎症が主役かどうか)と体質(胃・腎臓など)**で選び方が変わります。
カロナール(成分:アセトアミノフェン)
向いている症状
- 発熱
- 頭痛
- のどの痛み
- 風邪の熱・だるさ
- 筋肉痛など「軽〜中等度の痛み」
特徴(メリット)
- 胃への負担が少ない
- 腎臓への影響が比較的少ない
- 「まず安全に使いたい」「持病があってNSAIDsを避けたい」ケースで選びやすい薬です。
苦手なところ(弱点)
- 腫れや強い炎症が前面に出ている痛み(関節炎の強い痛み、強い腫れを伴う痛みなど)では、効きが物足りないことがあります。
ロキソニン(成分:ロキソプロフェン=NSAIDs)
向いている症状
- 腫れを伴う痛み
- 関節痛
- 捻挫など外傷後の痛み
- 歯痛 など
特徴(メリット)
- 炎症を抑える力が強い
- 「ズキズキ・腫れて熱っぽい」タイプの痛みに強いのが特徴です。
注意点
- 胃荒れ(胃痛・胃もたれ)
- 腎機能への負担
- むくみ・血圧上昇 などが出やすいことがあり、体質や状況によっては胃薬を併用することも多いです。
どう使い分ける?
- 腫れ・炎症が主役の痛み → ロキソニンが得意
- 胃にやさしさ優先/熱や軽めの痛み → カロナールが向きやすい
迷うときは、症状だけでなく「胃が弱い」「腎臓が心配」「持病や内服がある」など背景も大事。気になる場合は医師・薬剤師に相談してください。
よくある質問(FAQ)
- Q1:市販のタイレノールと効果は同じ?
→有効成分は同じアセトアミノフェンですが、1錠当たりの量や添加物が異なります。処方薬は用量調整の自由度が高く、医師管理下で安全性が担保されます。 - Q2:妊娠中でも飲めますか?
→妊娠中に最も安全性が確立した解熱鎮痛薬ですが、必ず主治医に相談し、最小有効量・最短期間の原則を守りましょう。 - Q3:お酒を毎日飲む人はどうすれば?
→アルコール代謝とアセトアミノフェン代謝が競合し、肝障害リスクが上がります。飲酒量が多い方は1日2,000 mg以内を目安に、定期的な肝機能検査を行います。
まとめ・受診案内
カロナールは「効かなければ量を増やす」というシンプルな戦略でしっかり鎮痛効果を得られ、胃腸・腎臓にやさしい薬です。だからこそ“飲み過ぎても平気”と誤解されがちですが、肝機能という盲点を忘れてはいけません。自己判断での長期服用は避け、必ず医師の定期チェックを受けましょう。
痛みが続くと生活の質(QOL)は確実に低下します。「痛みに慣れる」のではなく、「痛みを適切に抑える」ことで、リハビリや運動療法の効果も最大化されます。気になる症状があれば、どうぞお気軽に豪徳寺整形外科クリニックへご相談ください。
この記事のポイント(要約)
- カロナールは胃腸・腎臓への負担が少なく、高齢者でも使いやすい第一選択の鎮痛薬。
- 鎮痛効果は用量依存性があり、最大1回1,000 mg・1日4,000 mgまで段階的に増量できる。
- アルコール多飲や肝疾患がある場合は肝障害リスクが上がるため、定期的な肝機能検査が必須。
- 当院では初期投与→増量→採血フォローの流れで安全性を担保。
- 市販薬との違いは用量設計の柔軟性と医師のモニタリング体制。
- 痛みを我慢せず、適切な鎮痛とリハビリを組み合わせることで早期回復を目指せる。
- 気になる症状や薬の疑問は、豪徳寺整形外科クリニックに気軽に問い合わせを。
豪徳寺整形外科クリニックの受診をご希望の方へ
- 所在地:東京都世田谷区豪徳寺3-1-52
- アクセス:小田急線「豪徳寺駅」徒歩5分/東急世田谷線「山下駅」徒歩5分
- 診療時間:平日 9:00-12:00 / 14:30-18:00、土曜 午前のみ
- 電話:03-5451-7878
※当院の予約は時間帯予約制(30分幅)です。予約なしでも受診可能ですが、混雑状況によりお待ちいただく場合があります。