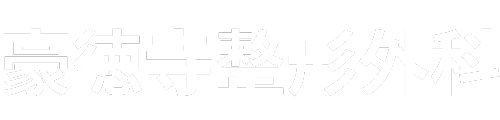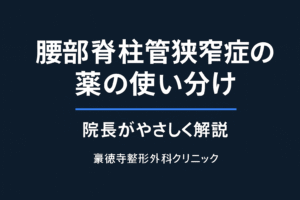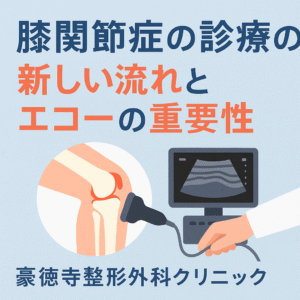内側半月板後根断裂(MMPRT)とは? |豪徳寺整形外科 経堂 豪徳寺 梅ヶ丘
膝の「半月板(はんげつばん)」は、膝の骨どうしのクッションです。内側半月板の“根っこ”(後ろ側の付け根=後根)が切れてしまうケガ/変性が 内側半月板後根断裂:MMPRT(Medial Meniscus Posterior Root Tear) です。中高年、とくにO脚ぎみ・体重負担が大きい方に多く、階段やしゃがみ動作のあとに「膝の後ろ(内側寄り)がズキッと痛む」「ポキっと鳴ってから痛くなった」などの訴えがよくみられます。
このページの要点(まずここだけ)
- MMPRTは“半月板が効かなくなる”ケガで、放置すると関節に負担が集中し、変形性膝関節症の進行が早まることがあります。
- 診断は問診・診察に加え、MRIが決め手です(レントゲンだけでは写りません)。
- 保存治療(体重管理・リハビリ・鎮痛薬・装具など)で痛みが落ち着くケースもあります。
- 活動量や年齢、膝のアライメント(O脚度合い)などをふまえ、**関節鏡下の縫合(プルアウト修復等)+骨切り術**で機能を取り戻す選択肢があります。
- どちらを選ぶかは “今の膝の状態と将来像” を一緒に見ながら決めましょう。当院では丁寧に評価し、最適な計画をご提案します。
どうして起こる?(原因と背景)
半月板は外周が骨に“根っこ”で固定され、全体にかかる力を“輪っかの張力(フープストレス)”で受け流しています。後根が切れると輪っかがほどけ、クッション機能が一気に低下。その結果、内側の関節軟骨に負担が集中し、膝の内側が痛む・腫れる・こわばるといった症状が出ます。
起こりやすい背景には次のようなものがあります:
- 年齢とともに半月板が弱くなる変性の影響
- **O脚(内反)**で内側に荷重が集まりやすい膝のアライメント
- **体重負荷(BMI)**が高い/立ち座り・深いしゃがみ動作が多い生活・仕事
- スポーツ外傷や、軽い動作での「ポキッ」というエピソード
こんな症状が多い(症状の特徴)
- 膝の後面〜内側後方の痛み(階段下降・立ち上がり・しゃがみで悪化)
- 痛みの発作の前に**「パキ/ポキ」**などの音や感覚
- 腫れ・可動域の低下(曲げづらい、伸ばしづらい)
- 内側関節裂隙の圧痛、深屈曲での痛み
- 慢性化すると**半月板の外側へのはみ出し(メニスクス逸脱)**により内側の荷重痛が持続
どうやって診断する?(検査)
1)診察
既往歴や発症状況をうかがい、圧痛点・可動域・アライメント(O脚の程度)を確認します。
2)画像検査
- レントゲン:骨の変形や関節の隙間を評価。ただし半月板自体は写りません。
- MRI:MMPRTの診断に有用です。矢状断で半月板が淡く消えて見える**“ゴーストサイン”**、冠状断・軸位断での放射状断裂像、**半月板逸脱(3mm以上など)**の評価を行います。
- 超音波:半月板の逸脱や関節水腫の確認に補助的に用います。
保存治療(まずは痛みを抑え、膝を守る)
**「痛みを落ち着かせ、日常生活を守る」**ことを目的に、患者さんの年齢・活動量・膝の変形度合いを見ながら次を組み合わせます。
- 活動調整と杖・サポーター:深いしゃがみ、階段での急な荷重は控えめに。
- 体重管理:体重の数kg減でも膝の内側負担は確実に軽くなります。
- 運動療法(リハビリ):大腿四頭筋・股関節外転筋の強化、ハムストリングス・下腿三頭筋の柔軟性改善。
- 薬物療法:アセトアミノフェン、NSAIDsなどを症状に応じて使用。胃腸・腎機能・他のご病気に配慮します。
- 関節注射:ヒアルロン酸など。痛みの緩和に一定の効果が期待できます(効果や回数は個人差)。
保存治療で痛みが落ち着く方もいますが、半月板の機能そのものは断裂前に完全には戻らないため、将来的な軟骨負担をどうコントロールするかがポイントです。
手術治療(関節鏡下修復の考え方)
目的は「半月板の輪っか(フープ機能)を回復し、内側関節の負担集中を減らす」ことです。多くは関節鏡下に糸で後根を骨に縫い直す術式(プルアウト修復/アンカー修復)を行います。必要に応じて、**O脚が強い方では骨切り術(HTO)**と併用して荷重線を調整することも検討します。
適応の目安
- 痛みが持続し、日常生活や仕事・スポーツに支障がある
- MRIでMMPRTが確認でき、半月板の修復が技術的に可能
- 内側軟骨の高度摩耗や強いO脚がある場合は、術式の追加(HTO)や別治療の検討
保存 vs 手術:どう選ぶ?(意思決定のポイント)
短期の痛みコントロールを最優先にするか、中長期の関節保護をより重視するかで選択が変わります。年齢、活動度、O脚の程度、軟骨のすり減り具合、既往歴(糖尿病・腎機能など)を総合評価します。
- 保存治療が合うことが多い方:
- 痛みが軽度〜中等度で、日常生活の調整で十分コントロールできる
- 活動性が低い/膝の変形が進んでおり、修復のメリットが小さい可能性
- 手術治療を検討しやすい方:
- 痛みが持続・増悪し、仕事やスポーツに支障
- MRI所見が明確で、修復で機能回復が期待できる
- O脚が中等度以内、軟骨の残りが保たれている
当院では、「将来どんな膝でいたいか」を一緒に言語化し、保存・手術・骨切りの組み合わせを含めて最適解を共同意思決定します。
予防と再発対策(生活のコツ)
- 体重管理:1kgの体重減は膝の内側への繰り返し荷重を確実に軽減します。
- フォームの見直し:しゃがみは浅めに、立ち上がり時は膝が内側へ入らないよう股関節から動かす意識を。
- 筋トレ&柔軟:大腿四頭筋・殿筋の強化、ふくらはぎ・ハムストリングスのストレッチ。
- 段差の上り下り:荷重は痛みのない範囲で小刻みに。手すり活用を習慣に。
当院での対応
- 詳細評価:X線、必要に応じてMRI・超音波での半月板逸脱評価
- 保存治療の最適化:生活指導・運動療法・装具・投薬・関節注射の組み合わせ
- 手術連携:関節鏡下修復や骨切り術が必要な場合は、提携医療機関と連携してタイミング・術式・リハビリ計画まで
- 復帰支援:仕事・家事・スポーツそれぞれの復帰目標を共有し、段階的リハビリを最後まで伴走
よくある質問(FAQ)
Q1:放っておくとどうなりますか? A:痛みが落ち着くこともありますが、半月板のクッション機能低下は残ります。内側軟骨への負担が続くと、変形性膝関節症が進みやすいとされています。早めの評価をおすすめします。
Q2:手術は必ず必要ですか? A:いいえ。年齢・活動度・アライメント・軟骨の状態で適応が変わります。保存で十分な方もいます。手術は将来の関節環境を守る目的で検討する選択肢です。
Q3:術後はいつ走れますか? A:一般的に3〜4か月以降に軽いジョギングへ段階的に進めます(個別差あり)。競技復帰はさらに評価しながら計画します。
Q4:再発はしますか? A:O脚や体重負荷のコントロール、深屈曲を避ける生活工夫、筋力と柔軟性の維持が重要です。必要に応じてインソールや装具も使います。
まとめ(今日のポイント)
- MMPRTは“半月板の根っこ”の断裂で、クッション機能が低下し、膝の内側に負担が集中します。
- 診断にはMRIが決定的です。レントゲンは骨の評価に用います。
- 保存治療で日常生活を守りつつ、手術修復は中長期の関節保護を目的に検討します。
- O脚の程度・軟骨の状態・生活目標に合わせて、最適な組み合わせ(保存/手術/骨切り)
- 当院では評価〜治療〜復帰まで一貫してサポートします。お困りの方は遠慮なくご相談ください。